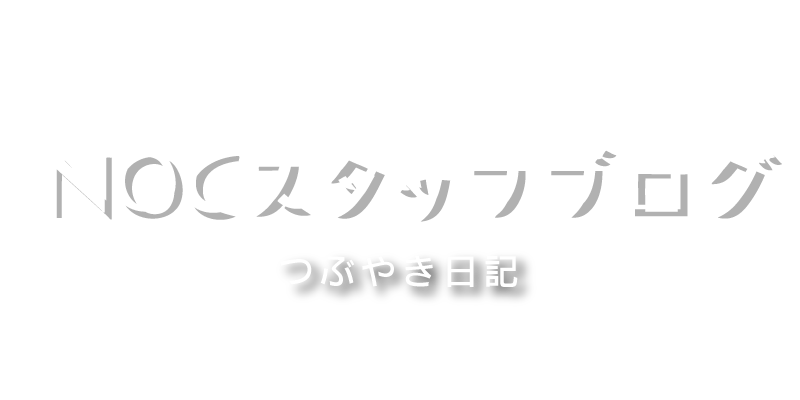1週間も前の話ですが、ニセコの秀峰「羊蹄山」に登ってきました。
羊蹄山は蝦夷富士とも呼ばれる円錐形の成層火山で、その美しい姿は北海道随一だと思います。美笛峠や中山峠を越えて後志の国にはいるとまず目に入るニセコのランドマークでありまして、洞爺湖からもその姿を望むことができます。
登山口は、「比羅夫」、「真狩」、「京極」、「喜茂別」の4箇所で、比羅夫と真狩が人気のようです。今回も比羅夫ルートから登ることにしました。
羊蹄山は0合目からの登山ですので、標高は1898mとそれほど高くないものの、1日がかりの行程になります。また独立峰で山頂部は風が強く、雨風をしのぐ場所があまりないので、ある程度の装備も必要です。
1合目を過ぎて急な坂を登りきったあたりに、風穴というサインがあります。

山の内部までつながっているこの穴から、常に冷たい空気が出ています。この風穴は羊蹄山のふもとの至る所にあり、昔は食糧貯蔵庫に活用していたところもあるとか。

ただ風穴の前に立つだけでは冷気は感じません。冷たい空気は下を流れますから、地面すれすれに手をかざしてください。真夏でも冷凍庫を開けたような感覚です。
<つづく>