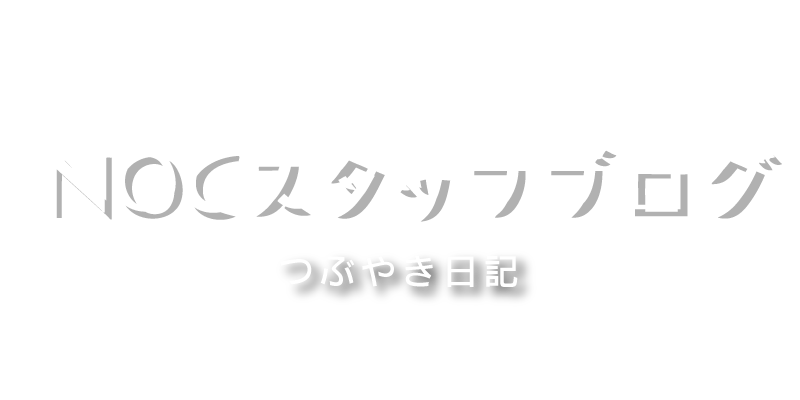ニセコアウトドアセンター入口の花壇でラベンダーが咲き始めました。
ラベンダーと言えば富良野と思われるでしょうが、ニセコでも数か所でラベンダー畑がみられます。
実はニセコ町の町花もラベンダーなんです。
これからもっと株分けして増やす予定ですので、ぜひ遊びがてら見に来てください。

月別アーカイブ: 2009年7月
ニセコ消防団実演
ガイドのSさんはニセコ消防団に所属しています。年に数十日かは夕方に訓練をしているそうで、仕事が終わるとダッシュで帰っていきます。
先日、消防団の消防実演が行われ、見学させていただけるということなので、見に行ってきました。

ビシッと整列した姿は、頼もしさを感じるとともに、訓練の厳しさを物語っています。

放水の実演のするSガイド。頼もしいです。

最後にニセコ小学校の横で、消火演習。皆さんキビキビ動いていました。
消防団の皆様のこのような努力のおかげで、われわれも安心して生活が送れるのだなと、感謝せずにはいられない思いでした。
名古屋の名物1
長良川シリーズ名古屋編です。
岐阜の帰りに名古屋で1泊でした。今回の集まりで知り合った名古屋の方に名物を尋ねたところ、「”ひつまぶし”と”みそかつ”は絶対食べて帰りなさい」と有名店を教えてくれました。
一緒に聞いていた方が、「ついつい”ひまつぶし”と言ってしまうね」と言ってましたが、私もついつい”ひまつぶし”と言いそうになります。
ホテルにチェックインし、インターネットで教えてもらった有名店の場所を調べます。まずは”ひつまぶし”の名店「ほうらいけん」。中華屋さんのような名前ですが、なかなかの繁盛店で1時間待ちとか普通にあるそうです。なるべく夕食時間に重ならないよう遅めに行ったのですが、40人ほどの行列ができていました。それではと、”みそかつ”の名店「やばとん」にいくも、こちらも大行列。
名古屋の繁華街をうろつきながら、時間をつぶすことにしたのですが、名古屋コーチンだの、手羽先だの、きしめんだの、味噌煮込みうどんだの、興味をそそるものが目につきます。いっそそれらを食べようかという思いにかられましたが、せっかくの名古屋で”ひまつぶし”、いや”ひつまぶし”は外せないな、ともう一度「ほうらいけん」にいくと、行列が20人ぐらいに減っています。結局一人だったので、15分程で店内に入れました。

そしてこれがひつまぶし。おひつの中に細かく刻んだウナギとご飯が入っています。混ぜて食べるのもよし、薬味と食べるのもよし、お茶をかけて食べるのもよし、と3種の食べ方が楽しめます。隣の人の食べ方を盗み見ながら食べました。お茶をかけるのは抵抗がありましたが、それが一番うまかった。
長良川
長良川シリーズです。
先月長良川に行きまして、先日少しだけ紹介したのですが、まだ他に面白いものがたくさんあったので紹介しています。

岐阜市内より長良川上流を望む。右端に麓が写っているのが岐阜城のある金華山、川の向こうに屏風山があり、地元では岐阜富士というそうです。

長良川といったら鵜飼です。鵜飼で使う木造小舟が係留されています。よく見たら足元にも係留用のステンレス環があり、ここまで増水するのか?と思ったら!

なんと川沿いのビルの2階部分にも係留ロープを巻き付ける金具が埋め込まれています。
ここまで増水することってあるのでしょうか?それより誰がロープを縛るんだろう?命がけですね。
鵜飼
長良川シリーズです。
鵜飼舟には乗れなかったのですが、岸から見てました。
鵜飼で鵜を操る方たちを鵜匠と呼びます。鵜飼の行われる川のすぐ近くに住んでいて、昼にちょっとのぞかせていただきました。

海鵜を使用しているようです。羽を切っているので、飛んでは逃げないそうだとか。
夜、鵜飼が終わったころにもう一度お邪魔しました。
木箱で3~4枚、100匹ぐらいの収穫でしたが、鵜匠さんは「顔が不細工や」とほとんどはねていました。
売り物になるのは、ほんの10匹ぐらいだったようです。漁獲量も相当減少しているそうです。

鵜飼が終わったら家族総出で片付けを行っています。鵜飼のとき付ける腰蓑をつけさせてくれました(写っているのは同行者)。
とても親切にお話を聞かせていただき感謝しています。
この界隈は長良川独特の地域性があり、非常に面白かったです。北海道では絶対に見れない街並みと暮らしです。

鵜飼は完全世襲制。跡継ぎがなければ、養子をとるそうです。

モナカにアイスを詰めて売っています。あついのでなまらうまかった。
ミツガシワ咲いています。
神仙沼のミツガシワが咲き始めました。
これから群落が見れます。
エゾカンゾウも咲きはじめて、7月になったな~と実感です。

川の指導者養成講座in夕張川2
捕まえた魚を水槽に入れて観察しました。
エゾウグイが多く、産卵の時期を迎えているようです。

午後は夕張川本流で、安全管理についての実習です。
PFD(ライフジャケット)をつけて川に流されたり、スローロープの使い方を学びます。
実際に流される人と助ける人と組んで、レスキューのシュミレーションを行いました。

そのあと、カヌーを使っておこなう体験活動の進め方、カヌーの操作方法を実施し、カヌーが転覆した際の対処法を全員に実演してもらいました。

当日は気温も高く、川に入っていても気持ち良かったです。
参加者の皆さんは3日間の講習でだいぶ疲れたようです。お疲れ様でした。